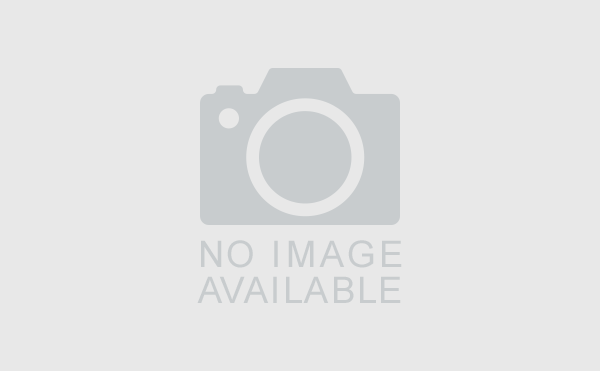電験二種合格のための,電験三種学び直しガイド(各論9):直流機
発電機
まずは簡単な直流発電機のモデルで発電の様子を考えてみたいところです。
電気的な負荷を負っているときに,機械的入力と電気的出力が等しくなっているかどうかも確認しておくとよいでしょう。
直流発電機が「直流の起電力」を得るために「何をしている」のか…これは結構複雑です。
どのタイミングでコイルが短絡され,どのように回路が切り替わっていくのか,「直流発電機の工夫を盛り込んだ」ミニマムなモデルで,その様子をじっくり考えてみましょう。
三種を受験するときは「整流」についてはあまり深入りしなかったかもしれません。なぜなら「難しい」からです。
しかし,ファラデーの電磁誘導の法則について深い理解を持った今なら,「整流」についてもよりよい理解を得られるはずです。
補極が「電気的中性軸のずれ」への対応のみならず,「リアクタンス電圧による整流の悪化」を防ぐ様子などが,よく理解できることでしょう。
様々な直流発電機の等価回路については,一度はそれぞれの「原理的な図」とセットで描くことをお勧めします。
「原理的な図」を描くことで,等価回路では表現しきれない部分などにも配慮ができるようになるでしょう。
電動機
「電動機は発電機と同じだ」と言われます。
たしかに「同じ」なのですが,その「動かされ方」はずいぶんと違いますから,電動機には電動機のテーマがあります。
まずは簡単な電動機のモデルで考えると良いでしょう。
そして「機械的負荷が増えたらどうなるか」「電源電圧を上げたらどうなるか」を考えてみます。
その際「公式から結論を押さえる」こともできますが,できればその結論に至るプロセスを細かく見ていくことをお勧めします。
結論に至るプロセスを細かく見ていくことで,結論に対して大きな納得感を得ることができますし,「磁場が弱まると速度が速くなる」という,一見直感とは反する結論も,十分納得できるようになることでしょう。
簡単な電動機のモデルで十分掘り下げて考えておけば,各種電動機の特性などについても「まぁ自明であろう」という感覚が持てるようになります。
電験三種講座の「機械3(直流機/電熱と電気加工〈ガイダンス〉)」の講義では,直流機について学び直すための「答え」と「ヒント」を数多く提供しております。
1日単位で受講できますので,ぜひ受講をご検討ください。